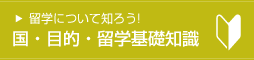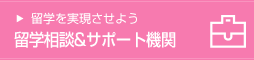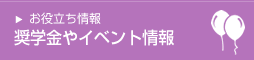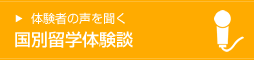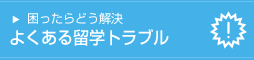まずは、幼稚園ボランティアです。こちらは、ウブドの幼稚園でみんなとても元気でした。最初はどうとっつけばいいか分からずに困惑しましたが、追いかけたり、怖がらせたりすることで、初日から彼らと仲良くなれました。また、折り紙を教えたのですが、これはかなり得意苦手(好き嫌い?)が分かれたようです。
例えば鶴を折っていても、途中形で投げ出してアイスクリームにしてしまったり、ふと振り返るともう崩してしまっていたり。。。でも、中には好きな子もいたようで、必死にこちらの腕をつかんで「次は?」といった表情で見つめ返す子もいて嬉しかったです。また、足し算や読み書きの練習も手伝ったのですが、2日目くらいからこれも得意な子と苦手な子がすぐにわかってきました。
苦手な子には丁寧に指を追ったり絵をかいたりしたのですが、どうもうまく伝わらないみたいで・・・。教えることに難しさを感じました。しかし、よく考えてみると、幼稚園生のころから足し算や読み書きを行っているというのは、結構レベルが高いと思います。自分は幼稚園生のころに足し算を習った覚えはないし、基本的にはずっと遊んでいた覚えがあったからです。次第に名前を覚えたり、何をしたら喜ぶかが分かってくると、どんどん彼らとの距離が縮まりました。しかし、最終日になるとそんな彼らとの別れが本当につらくなりました。
言葉や文化の壁を乗り越えて、毎日、追いかけたりボールを取り合ったりするだけで親密になれ、笑顔を絶やさなかった彼らとの別れは胸にぐっときました。
「さようなら」の歌を歌われながらひとりずつ別れを告げた時には、もう涙が出ていました。自分は、参加前にこのような記事をCECの体験談から読んだとき「そんな、まさか。」という思いでしたが、本当に胸が痛くなって自然と涙して
しまいました。言語の壁がありながらもこんなにも仲良くなれたんだなと改めて実感し、いつか彼らと会いたいなと思いました。
次に、日本語クラスのボランティアです。2回しかありませんでしたが、改めて日々使っている日本語のむずかしさを知りました。単純な発音から細かな文法まで、必死に勉強している彼らを見て、自分らの使っている言語がどうしてこんな複雑なんだろうと感心しつつもどこかやりきれない気分でした。また、中には日本に訪れたこともある子がいたり、日本のアニメや音楽が好きな人がいたりしたので、会話が楽しくなりました。もっと回数を増やして彼らと接していきたかったので、時間が少なくて残念です。
最後に、孤児院のボランティアです。こちらは、幼稚園より日数が足りなかったのですが、貧しい人々たちに裕福な国で育った自分が何をできるかをよく考えさせられました。孤児院では、聴覚に障害を持つ子たちや、学校にも行けない子が多かったです。彼らとはサッカーやバドミントン、トランプを通して仲良くなりました。しかし、一番の壁は言語ではなく、その環境でした。迂闊に「名前は?」「どこ出身?」という愚直な質問をしてしまうと、向こうはその背景から傷つくことがあるからです。なので、共に遊びながらも、適切な距離で親しくなっていきました。中には自分から名前を教えてくれたり、バドミントンやろう、などと声をかけてくれる子もいて、そういう時はとても嬉しかったです。また、驚いたことに、学校に行っている孤児院の子でひとり、とても数学に強い子がいました。トランプで「24ゲーム」や「神経衰弱」をやったのですが、それを通して彼の計算力と記憶力に驚かずにはいられませんでした。しかも、自分より年下という点に驚き(笑)。他にもサッカーがうまい子、折り紙が自分より上手い子がいて、そんな彼らを見ていると、彼らにも立派に誇れる取り柄があるんだなって素直に思えました。
けれど、ここで痛感したのは、やはり自分が彼らに何をしてあげられたのか、何を残すことができたのか、という点です。きっと自分らに求められていることは彼らの心を明るくし、毎日を元気づけることです。なので、Facebookなどで今後も連絡を取り合い、彼らに「あの日本人と友達になって良かったな」「毎日をもっと楽しまなきゃ」という考えを維持させることだと思います。今回はそのことについて、日本に帰国してから気づきました。幸い、同プログラムに参加していた友人のおかげで彼らと今も関係を維持できています。先日は向こうから夜に「Hayyy Ryooo」「What are you doing Ryo??」等と連絡が来て本当に嬉しかったです。やはり、現代は非常に簡単にネットワークを維持できる時代なので、それを最大限に利用すべきなんだなと改めて感じました。そして、近況などをこれからもお互いに伝え合うことで、なにか彼らに残すことができればいいなと感じました。どちらも非常に有意義なボランティアでした。